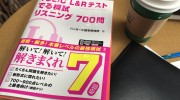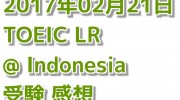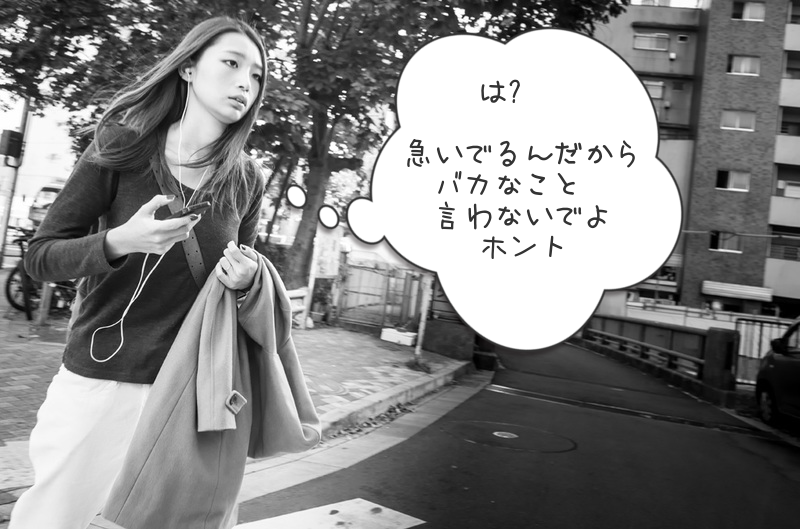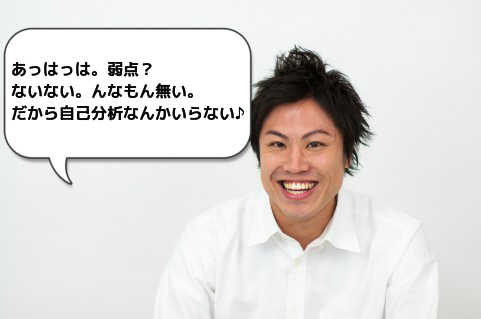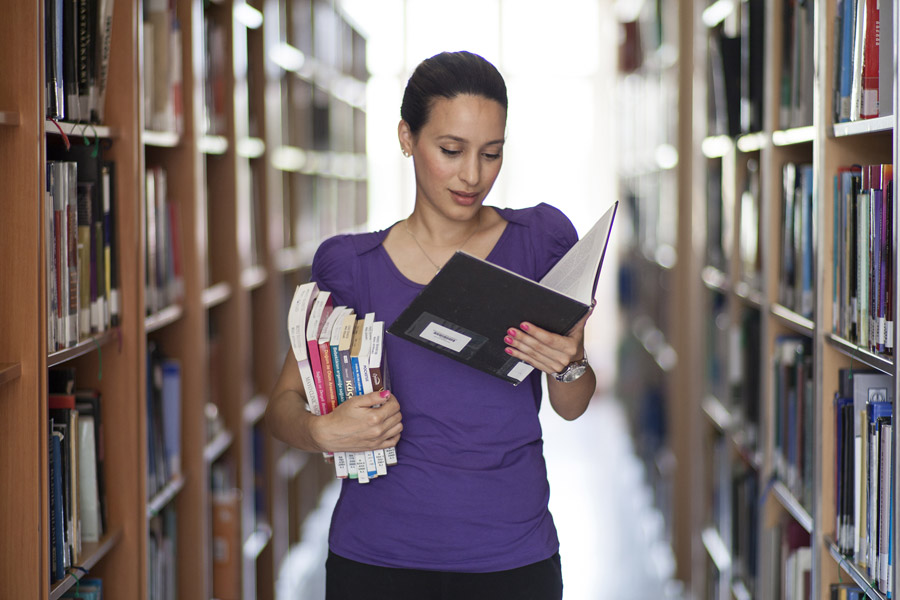海外で英語を使って仕事をしていると色んなことを感じます。
お世辞にも上手とは言えない英語しか使えない(クセが酷かったり間違いが多い)にもかかわらず、率先して英語を「使おうとする」人と、そこそこ英語を使えるにもかかわらず「使おうとしない」人。
言わずもがな、前者は英語のスキルも次第に改善していき、仕事も上手くいき、周りの評価も高くなります。
他方、後者は英語のスキル向上は認められず、(外国人との)仕事は上手くいかず、周りの評価も低くなってしまいます。
J君とW君
私の部下のインドネシア人にこんな二人がいます、と言うかいました。
37歳のJ君と25歳のW君。
J君は私より年上ですが、インドネシア人の部下。
で、W君は何を隠そう、2016年末に青天の霹靂の如く退職してしまった彼です。
【関連記事】 部下が会社を辞めると言い出したので人生初めて英語で引き止めてみた
なお、J君は未だ勤務中です。
この二人が正に以下のようにカテゴライズできてしまうのです。
J君 (37歳) = そこそこ英語を使えるにもかかわらず「使おうとしない」人
W君 (25歳) = お世辞にも上手とは言えない英語しか使えない(クセが酷かったり間違いが多い)にもかかわらず、率先して英語を「使おうとする」人
W君は、もう当社にいないので何を言っても仕方ありませんが、大変優秀な営業マンでした。
質問があったら率先して聞きにきたり、外国人 (日本人、韓国人、アメリカ人など)に対しても英語でコミュニケーションをとっていたんです。
一方、駐在員ってどこの国に行っても、その国の母国語を喋るよう推奨されています (母国語が英語の国も多くありますが)。
従いまして、本来であれば駐在員がその国の言葉を積極的に学び、意思疎通を取るべきなんです。
とは言っても、やはり世界の共通言語は英語です。
現地語をネイティブレベルまでマスターすれば問題ないのでしょうが、そうでなければ伝達ミスが起こり得るのです。
ということで、現地語を勉強することが推奨されているものの、やはり「英語」が大事なんです。
話を戻すと、W君はその辺をよく理解していたと思います。
食事の時や、立ち話の時にはインドネシア語を話してくれたりしましたが、それ以外は基本的に英語を使っていました。
いや、使おうとしていました。
苦手なのは見ていて分かります。
英語のみに限らず、当社の商品・サービスを積極的に学ぼうという姿勢も感じることができました。
私が一緒にした期間は9ヶ月間だけでしたが、将来、リーダーに抜擢しようとも考えていました。
とまぁここまでW君のことを話せば、J君をどう形容したいかお分かりでしょう。
J君に、TOEIC LRしか勉強しない日本人の闇を垣間見た
J君は頻繁にインドネシア語で私に語りかけてきます。
で、反応を見て, “Ha Ha Ha, it means xxx”と簡単な英語で説明をしてくるんです。
赴任当初は特に疑問に感じず、私も”Oh, I see! It means xxx !!”とか反応していましたが、周りの駐在員の話を聞くと、
「Jって、そもそも英語で話そうとしないんだよな」
「インドネシア語でインドネシア人だけに話すようにして、駐在員と線を引こうとしている」
「英語で話そうとしてくれないから、普段から何を考えているかわからない」
などなどの評判・噂・意見が出てきたんです。
こういった情報をそのまま鵜呑みにしたわけではありませんが、私も思い当たる節がありましたので。
で、この二人を比較して、私が最初に感じたことは、「やっぱり英語 (語学)は使ってナンボだな」っていうことで、「日本人は恥ずかしがらずにどんどん英語を使おう」ってことでした。
ただ、こういったことは個人の自由ですから強く主張しても仕方ないかなと。
さらに、TOEICを勉強し続けている私が感じたのは、「TOEIC LRの勉強に終始してしまっている日本人って、J君と同じではないか」ってこと。
2016年にTOEIC LRも新形式となり、その人気は衰えを知りません。
【関連記事】 TOEIC(R)テスト 出題形式一部変更を発表 【第210回公開テスト(2016年5月29日)より】
TOEIC LRを愛してやまない私としては嬉しいことですが、いつまでもTOEIC LRの勉強に固執してしまうのはよろしくないのではないでしょうか。
もちろん、いつまでたってもターゲットスコアを取得できないのでは卒業もできませんが、せいぜい2年くらいでTOEIC LRは卒業すべきです。
そして、TOEIC SW、英検準1級・英検1級、国連英検A級、特A級などの「話す英語試験」に取り掛かったり、仕事としての実践に移るなりしないと、J君と大差ないことになります。
せっかくTOEIC LRで多くの英語スキル (といってもリスニングとリーディングだけですが)を学んで、英語を使えるステイタスがあるにもかかわらず使おうとしないのは、間違いなく日本人が抱える闇です。
(韓国人はある種、目的意識がはっきりしています。一流企業に入るためにTOEICハイスコアが必要なわけですから)
某巨大日系企業のインドネシア人
先日、某巨大日系企業のローカル(5人)を接待しました。
そのうちの一人が結構な量の日本語を話せたんです。
「へぇ〜、5人もいると一人くらい日本語を話せる人がいるんだなぁ〜」と感心したと同時に私も頑張らねばと思い知らされました。
その会話の1時間後、まさかのもう一人のインドネシア人が、「モウオナカイッパイデスカ?」と私に尋ねてきました。
「あらっ!? 君も日本語話せるの??」
「ハイ、サイキン・・・ニネンマエ? ナゴヤにイッテイマシタ」
「は 〜、だったらさっきの会話の中に入ってきても良さそうなのに・・・」
性格もあると思います。
シャイだったり空気読んだり (上司が喋っていたら話さない)とか。
でもやっぱり「話そうとする人」と「話そうとしない人」には大きな違いが出てきてしまいます。
「良い or 悪い」で言うと、やっぱり話そうとする人の方が「良い」わけですよ。
話そうとしない人がダメとは言いません。
別に英語や日本語を話せるから、そこを評価して欲しいとそもそも思っていなかったりしますし。
従いまして、「やっぱり英語 (語学)は使ってナンボ」だから「日本人は恥ずかしがらずにどんどん英語を使うべし!」とは一概に言えないところもあると思います。
が、理解しておくべきは、そこには大きな違いがあるということです。
私が考える英語習得までの考え方は以下のとおりです。
英語を使える (= 話せる・聞き取れる・書ける・読める)人は、「英語を話そうとするから、話せる」であり、「英語を話せるから、話そうとする」ではない。
同様に、
英語を使えない人 (= 話せない・聞き取れない・書けない・読めない)人は、「英語を話そうとしないから、話せない」のであり、「英語を話せないから、話そうとしない」ではない。
ここは是非ともTOEICを勉強している皆さんに認識しておいて頂きたい点ですね。